初盆(新盆)とは
初盆(新盆)とは、故人が逝去されてから初めて迎えるお盆のことを指します。七七日忌明け法要前(四十九日以前)にお盆を迎える場合は、初盆(新盆)は翌年におこなうことが一般的です。
初盆(新盆)時期Season
8月13日~8月16日(旧暦の7月)に行われる地域が全国的に多いですが、東京や関東の一部では1か月早い7月(新暦の7月)に行われることもあります。15日を中日として、13日に故人をお迎えするために迎え火を行い、故人が戻っていってしまう16日に送り火を行います。
初盆をむかえるにあたっては、盆飾りやお供え物の確認、ご自宅でのご供養の打ち合わせなどを、お寺さんにご相談をしておきましょう。
地域や宗派での風習などが違うことがありますので、事前の確認は必要となります。
初盆の準備Preparation
盆棚(精霊棚)と呼ばれる棚をつくり、盆棚の飾りつけをします。棚の上には、お位牌、お供え物、故人の好物だった食べ物などをお供えします。お仏壇の横や手前に盆棚を用意して、盆飾りやお供えを飾って、故人をお迎えすることがなによりのご供養となります。
「精霊馬(しょうりょううま)」とよばれる、お供え飾りはお盆には一般的です。良くある昔ながらの飾りは、馬と牛に見立て、盆棚に飾ります。馬に乗って早く来ることができるように牛に乗ってゆっく戻ることができるようにと、言われております。

白提灯Shiro-chochin
初盆にあたっては、盆飾りとして、白い提灯を用意します。故人がはじめて戻ってくるときに迷うことがないように、迎え火で灯した白い提灯を目印として飾ります。そして、初盆の間に飾っていた白提灯は、送り火の際におがら等と一緒に焚き上げ、ご供養といたします。
初盆法要Hoyo
初盆ではご親戚様ほか、故人様とご縁のあった方々にお声をかけお集まりいただき、故人の生前のお話などででしめやかにご供養をいたします。そして、ご自宅のご仏壇の前で菩提寺の僧侶に読経をしてもらうのが一般的です。
墓地が近ければそのままお墓参りに行くこともありますし、初盆法要が済んだ後にご会食を行うこともございます。このように、初盆はきちんとした供養の式を行うのが習わしです。そのため、盆飾りやお供え物、お客様への御食事まで、気を配る必要があります。
初盆のお返しOkaeshi
お供え物をお預かりする、また御仏前(御佛前)をお預かりしますので、お客様がお帰りの際にご挨拶方々お返しの品をお手渡しでお渡しします。一般的には、3,000円~5,000円ほどのお供え物や御仏前になりますので、1,000円~2,000円程度の品物をご用意します。消えものといわれる商品(食べてなくなるもの、使ってなくなるものなど)が多く選ばれております。こちらも、地域での違いはありますので、事前に確認が必要となります。
お品物には掛け紙(のし)を付けます。水引の上は「初盆志」または「志」とし、水引の下はご葬家様の名字、または〇〇家、とご用意します。
ご挨拶状は、香典返しの際に挨拶状をお渡ししているので、初盆の際にはご用意してお渡しする必要はありませんが、ご希望がありましたら、初盆にあわせた【定型文】初盆お礼はがきをお付けすることができます。
また、遠方から御仏前を頂戴した場合には、ご挨拶状のかわりに、こちらの【定型文】初盆お礼はがきをお品物と一緒にお送りすることもできます。お返しの品をお手渡しするのと同様に、掛け紙(のし)を「志」「初盆志」として、宅配便などでお送りいたします。また一般的には、お預かりした御仏前に対して香典返しと同様に半返しで、お返しの品をご用意いたします。
初盆 掛け紙Kakegami
初盆のお返しの品には、掛け紙(のし)を付けてお渡し・お届けいたします。
水引の上に「初盆志」または「志」として、下にご葬家の苗字をいれます。
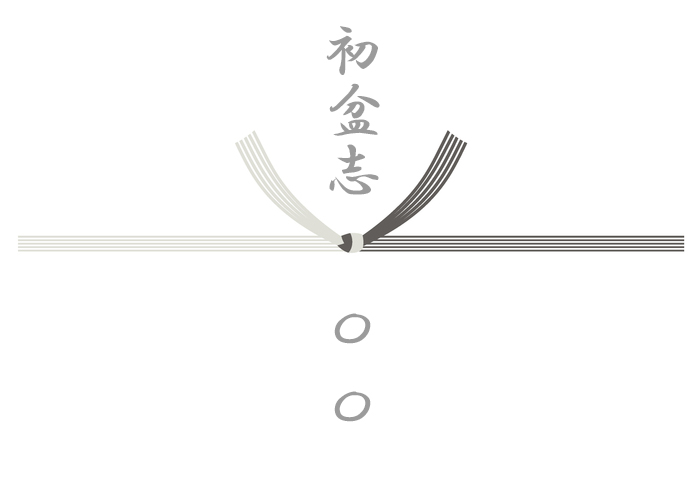
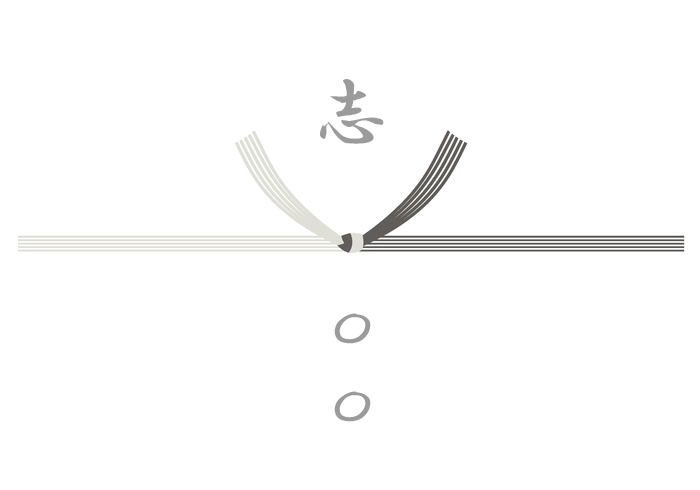
※のし紙を選択して、のし上は「志」を選択するか、フリー項目欄に「初盆志」とご記入をお願いします。
初盆お礼はがきOrei-hagaki
初盆のお返しの品をお送りする場合は掛け紙だけお付けする形でよろしいのですが、ご挨拶状などが必要なの場合にはご挨拶状にかえて、定型文初盆の御礼はがきをご用意しております。
初盆 お礼はがき 定型文
このたび 故人 初盆法要に際しましては 過分なる
御芳志を賜り誠にありがたく厚く御礼申し上げます
つきましては供養のしるしまでに心ばかりの品を
ご用意させていただきました
何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます
茲に改めまして故人生前中のご厚誼に感謝申し
上げますとともに 略儀ながら書中を以って御礼の
ご挨拶を申し上げます

※初盆お礼はがきは、お買い物の際にカートの中にて、ご指定をお願いします。


【営業時間】 AM10:00~PM5:30
(日曜/GW/夏季休業/年末年始を除く)







